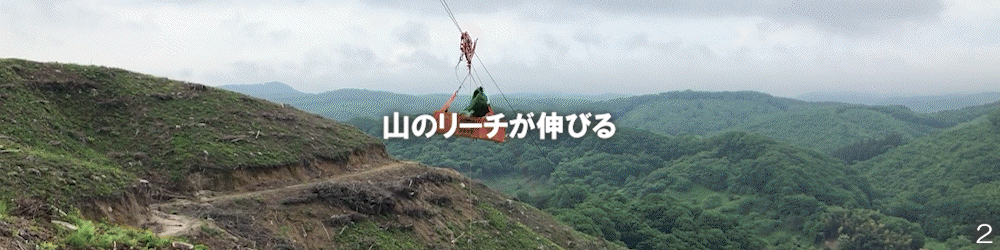簡単で頑丈な丸太橋の作り方
針金やクギを使わず、簡単で丈夫な丸太橋を作ってみませんか。

これまでジャンプして越えていたぬかるみや川を、こんなちょっとした丸太橋があるだけで安全に渡れるようになります。
簡単に作れますので、作り方をご案内します。

1.
手頃な丸太を2本用意してください。
径が10~15センチぐらいなら、さほど重くなく扱いやすいです。
できるだけ通直なものがいいですよ。

2.
ちなみに写真の丸太は径12センチ。
このぐらいの幅があれば、大人がゆったり歩くことは難しいですが十分歩けます。
長さが320センチ。
長さは場所に合わせてください。

3.
必要な道具は、左から
・クランプ ✕2個
・板きれ
・異形鉄筋 Φ10ミリ ✕長さ40センチ ✕3本(本数は丸太の長さによる)
・マーキングスプレー
・木工用ドリルビット Φ10ミリ (できるだけ長いもので、少なくとも丸太径以上のもの)
・インパクトドライバー
・金づち (大きめのもの)
※異形鉄筋の長さは、丸太径の2本分+10センチを目安にしてください。

4.
2本の丸太が隙間ができるだけ小さくなるよう並べてください。
そして、一カ所に板きれをのせてクランプで挟み、丸太が動かないよう固定してください。
これは仮留めです。
クランプを外しても面が分かるよう、マーキングスプレーをちょこっとかけておくと良いです。
また軽トラックの背中に乗せると作業しやすいですよ。

5.
丸太の横側の何カ所か選び、ドリルを使って横から下穴を開けます。
手前の丸太を貫通させますが、奥の丸太は貫通させなくてもかまいません。
異形鉄筋(Φ10ミリ)が入るよう、ドリルビットは10ミリのものをお使いください。
※9ミリ以下ですと、異形鉄筋をすんなり打ち込めず曲がってしまいますので注意ください。

6.
手前側の丸太の全カ所の下穴が貫通したら、クランプを外して、奥のほうの丸太についても下穴を貫通させてください。

7.
2本の丸太の下穴が全て貫通したら、金づちを使い、片方の丸太に異形鉄筋を打ち込んで下さい。
反対側からちょこっと頭を出したところで打ち止めます。

8.
他方の丸太の下穴に、飛び出した異形鉄筋の頭を差し込んで、2つの丸太を密着させます。

9.
異形鉄筋を打ち込みます。
両側から頭が飛び出すようにしてください。

10.
飛び出した異形鉄筋を金づちで曲げ、丸太にめり込ませます。
これで完成です。

11.
あとは好みによりますが、端をチェンソーで斜めに切り落とせばバリヤフリーになります。

12.
完成した丸太橋の姿です。
金物がまるで見えませんので、自然な感じの出来上がりです。

13.
これも好みですが、傾斜があるときは、滑り防止に切り欠きを入れてみてはいかがでしょう。
以上、簡単で頑丈な丸太橋の作り方でした。
よろしければお試しください。
(追記)面を平らにして作る別の方法
「橋の上面を平にしたい。」
「幅を広げてもっと歩きやすくしたい。」
という方は、丸太を縦挽き(縦切り)して、面を作ります。
半分に割れば、丸太の本数も節約できます。
厚みが半分になることでビスで組み立てられるようになります。
(事例1)こちらの動画で作り方をご覧ください。丸太バイスを使用して作成しています。
(事例2)
(事例3)
これらの事例で、丸太を縦挽き(縦切り)に使用したのは、丸太バイス「立介」です。
こちらの足下に映っている道具が立介。
安全に縦挽きができるようになりますのでお勧めします。